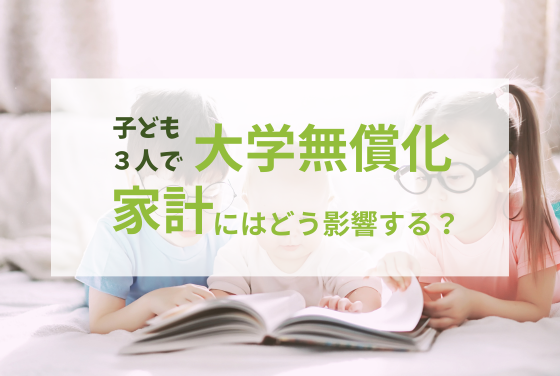”「異次元の少子化対策」をめぐり、政府は3人以上の子どもがいる多子世帯について、2025年度から子どもの大学授業料などを無償化する方針を固めた。所得制限は設けない。”
今月上旬にYahoo!ニュースを見てたら、いきなり入ってきたこのニュース。
検討ではなくて...いきなり決定なの!?ホントに?
衝撃でした。
これってつまり、返済の必要がない給付型奨学金のようなもの。
子ども3人以上いたら大学授業料などを免除するというのはすごい話です。
”給付型奨学金の条件を緩くする”、とか
”高校まで完全費用負担0”、とか
それでも良さそうなのに、いきなりアクセル全開で踏み込んできた印象です。
発表後に修正がはいり
3人全員免除というのは条件付き(3つ子以外は事実上不可能)
となりましたが、それでも間違いなく言えるのは「子ども3人以上いるとライフプランが激変します。」ということ。
FPの私が多くの家計のライフプランを作っていく中で、赤字になるのが多いポイントはズバリ大学進学費。
この支出負担で赤字になる人が多いので、家計は間違いなくよくなります。
大学進学における支出額をおさらい
文部科学省が出しているデータから入学金・授業料などを計算していくと、おおよそ以下のような感じになっているようです。
・国公立大学 約250万円(4年間)
・私立大学(文系) 約400万円(4年間)
・私立大学(理系) 約550万円(4年間)
教材費、施設設備費は学部や大学により大きく異なる上言及されていないので、今回はおいておきます。
この他に親の負担となるのは、いわゆる自宅外進学の時のアパート代・食費・光熱費。
新潟にお住まいの方だと自宅外進学率は75%にのぼります。
自宅外生活費を月あたり10万円と勘定すれば、4年間で480万円、約500万円です。
学費はともかくこの分さえ負担すればOK!となるなら、かなり肩の荷は下ります。
実際、親は学費で手一杯…。
と、この分の一部は奨学金やアルバイトで工面する学生がほとんどですからね。
大学無償化の詳細(2023年12月14日現在)
要点をまとめると、以下になります。
国公立は事実上全額補助になりますが、私立は自己負担となる部分もありそうです。
【国立大学】
・入学金 上限28万円
・授業料 上限54万円/年
【私立大学】
・入学金 上限26万円
・授業料 上限70万円/年
私立大学は上限より多いところがほとんどでしょう。
特に理系や医学系などでは、補助額をはみ出て自己負担が発生することになります。
その他の条件
医学部や薬学部などの6年制の学部については、最大6年間支援が可能。
大学だけでなく、短大や高専や専門学校に進学しても支援が可能。
ただし留年や出席率が低い場合などは対象から外れる可能性があり。
つまり第1子に「留年で大学に意図的に長く在籍してもらう」というような裏技は使えません。
第一子浪人なら期間を伸ばせそう。ですが予備校代もかかりますし、そんなことで子どもが人生を振り回されるのもおかしい話です。
親子の信頼関係のためにも、間違っても「学費のために浪人(留年)して」なんていうべきではありませんよね。
また、直近3年度全ての定員が大学等で8割未満、専門学校は5割未満の進学先では「無償化」にならない場合もあるようです。
定員割れしている進学先については、今回の補助を出すこともしないという意向です。
これから少子化でさらに定員割れの学校が増えることが考えられます。「どこでもいいから大学を出ておけ」という時代ではなくなったということでしょう。
子ども3人のカウント方法
当初は子ども3人いれば、「子ども全員が無償化!?」というノリで報道になりましたが、シビアな内容に改変されました。
最初の報道は誤報だった、というレベルですね。
対象となるのは、扶養する子どもが3人以上いる世帯の子。
例えば子ども3人で、第1子と第2子が大学に在籍していれば、2人とも対象となります。
ただ、第1子が卒業後に就職して扶養を外れると、扶養する子どもが2人となるため、第2子と第3子はその時点で対象外となります。
ん...これは...?
「前の児童手当と一緒のカウント!!」ですよね。
3人全員無償化を期待していた方々には、かなりがっかりする内容となりました。
なぜ敢えて持ち上げてから落とすのか。
子ども3人の場合、第1子は全額補助が期待できる
とはいえ、このシステムだと確実に計算できるのは3人きょうだいの場合の第1子。
大学以降の進学費用をほぼほぼ免除してもらえることになります。
なんだかんだ言っても、この支援は3人のお子さんがいる家庭には大きいものになります。
日々ライフプランの相談に乗っていても、一番の家計の鬼門は大学進学費。
その準備に心理的負担を感じている方が実際かなり多いです。
あなたはいかがでしょうか?
私もここの準備については、心理的負担感が大きいです。
そのため、子どもの人数を抑えるよう考えていた人は本当に多いのです。
しかしこの政策によって「3人のうち1人は確実に大学進学費の支出が減る。」となれば、心理的なハードルは下がりますよね。
2人目以降の完全免除は条件がやや厳しい
2人目が免除になるには、第1子が社会人になってしまってはダメです。
なので第1子が6年制の大学に行かない限りは、年が離れていると2人目はノーカウント。
2歳差きょうだいで浪人ナシ、の場合で考えてみましょう。
4年制大学に第1子が進むと、第一子は4年間免除。
2歳差の第2子は、第1子が卒業するまでの間の2年しか免除にならない、という感じです。
第1子が2年制の専門学校へ行った場合。
2歳差の第2子は、第1子卒業と同時に入学=全額負担ということになります。
とはいえ4年制大学前提であれば、2人目も1人目と年齢が4歳以上離れていなければ何かしらは恩恵を受けられます。
今子どもが2人いて、3人目を考えている方。
その場合は、年が離れていても第1子の補助は確実に新たに受けられます。
そういう意味では、子どもは2人と3人のケースを比較してもトータル大学支出額が大きく変わらないことになりますね。
3人目を産むかどうか、主に学費の経済的問題で躊躇している方のアシストになること自体は間違っていません。
実際は子ども2人を金銭面で断念するケースが多い
「子どもの数を増やすラストチャンス!」というのが本来の趣旨である政策。
正直、もうちょっとインパクトが欲しかったというのが私個人的な感想です。
少子化対策なのか。
子育て世帯への経済支援なのか。
どちらも中途半端になってしまっています。

というのも、そもそも日々ライフプランを作っていると、
「子ども2人」
を金銭面で断念するケースがとっても多いのです。
「2人→3人」のアシストももちろん大切。
人口再生産率を考えると「3人」を掲げたくなるのもわかります。
でも、そもそもそこに辿り着けてない「1人→2人」のアシストもしっかりしてもらったほうがいいと思います。
「1人→2人」のサポートをしっかりする。
その方が少子化対策という点では即効性があるように思います。
3人は金銭面もそうですが、晩婚化という背景もありどちらかというと体力・精神力的なハードルもあります。
2人の子育てはまだ現実的だし、出生数を増やすという効果も出やすいという印象が個人的にはあります。
徹底的に子育て世代優遇 の方向性
この他にも、子育て世代への優遇が話題になっています。
・住宅ローン減税の限度額を子育て世代だけ減少させず現状維持
・生命保険料控除の額を子育て世代だけ今より拡大
このような方針も確定となりました。
ただ...これらの施策は個人的にはちょっとどうなの?とも思います。
だって、これから家を買って住宅ローンをたくさん組まないとメリットはありません。
生命保険にもたくさん入らないとあまり控除されない。
つまり住宅業界・生保業界にたっぷりお金を使ってくれた人限定で優遇する、という政策。
ちょっといろいろと業界の力が働いている感じがするからです。
それはちょっと、我々が求める「優遇」とは違います。
控除額が増えるから~ という営業トークがこの先テッパンになるのでしょう。
でもこれは大間違い。
控除のために住宅ローンを増やしたり、生命保険にたくさん入るのは絶対に避けましょう。
住宅ローンは無理のない額が大事ですし、生命保険も必要最低分だけで十分です。
特に若い人ほどじっくり考えることにより将来が大きく変わってきそうですね。
PS 人生を長い目でみたプランが大切
あなたが今ちょうど住宅購入を考えているライフステージにいるのなら、新潟住まいのお金相談室がライフプランづくりのお手伝いができます。
お申込みは、こちらからどうぞ。
保険や住宅を売ることを目的にしない住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして、100%顧客サイドで顧客の理想とする家を安心・納得して買えるようにアドバイスを行う。そのスタイルが支持され、新潟県全域から年間100件以上の相談依頼を受けている。