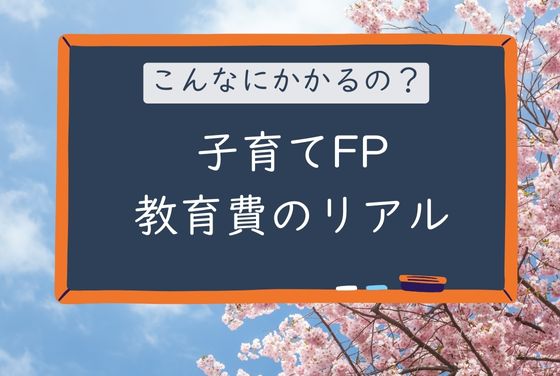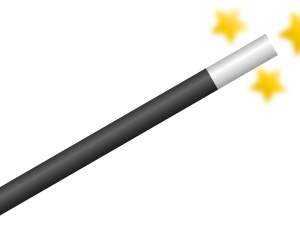次男がこの春から小学校に入学しました。
長男から通算して9年間通った保育園も終わり。
親としてもお世話になった先生側に会えなくなるさみしさがあります。
年長さんのの担任は、初めて担任を持つという若い先生でした。
いつも一生懸命に子どもたちに接してくれいて、子どもも「だいすき!」な先生。
初めての担任は大変だったかと思います。ですが、とても丁寧に関わってくれているのが親の立場からも感じられました。
卒園式では先生も保護者も涙があふれ、とてもいい思い出を作ってくださいました。
常に初心を大事にして、相手への思いを持って接する。ということの大事さを教えてもらった気がします。
4月から小学生になると、仲良しの多くが別の小学校へ進む次男。
最初は卒園をいやがっていましたが、先生から前向きな言葉がけをしてもらい、「小学校が楽しみ!」「友達100人作る!」と変化していきました。
ランドセルは兄の「だれもその色いないと思うよ」のアドバイスを聞きながらも、お気に入りをチョイス。
親としては他の人がどうかではなく、自分軸を持ってくれて嬉しい限りです。
(そもそも兄も学年でひとりの色ですが、気にしていませんが)
こだわりのランドセルを背負った入学式の子どもたちの笑顔の中には緊張と不安も隠れ見え、こうやって少しずつ大人になっていくのだと実感をしました。
さて、そんな大人に近づいてくる足音を大きく実感してくる中で、子どもの教育方針をどうしようかと私自身も深く考えるようになりました。
今日の記事はリアルの教育費についてかきます。
ちょっと長いので興味がある方のみお読みください。
ほぼ100%の親が想定以上に教育費がかかると感じている
私は仕事として相談者の方のライフプランを作成します。
その中で自分自身が経験して分かったことがあります。
それは、教育費って想像以上にかかるよねってことです。
例えば我が家の習い事費用の詳細は以下のようになっています。
(小4、小1の子ども2名)
スイミング:8,635円@2人=17,270円
音楽:9,185円@1人=9,185円
陸上:6,500円@1人=6,500円
合計:32,955円/月
習い事は月謝だけではありません。
スイミングのパンツやキャップ、楽器やテキストの購入、ウェア、シューズなど。
これらを月換算にすると余裕で10,000円超えてくるでしょう。
習い事が本格的なものであればあるほど、大会や試合の遠征・発表会、合宿など、ますます費用のかかる場面が増えていきます。
もちろんここに小学校の給食費・課外活動費、学童保育なども加算されていきます。
とはいえ、我が家は他の家庭と比較しても普通程度の習い事だと思います。
(まわりでは保護者はもっとしている人が結構多いです)それでも全部足すと月平均5万円の支出になっていることが分かります。
実は一般的なライフプランシミュレーションソフトのデフォルト設定では、習い事費用をあまり織り込んでいません。そのため、子育て期になると家計が想定以上に厳しくなることが多いようです。
これは習い事をはじめとした教育費の要素が強く影響してくることが実体験から分かります。
そのため私は相談者へのヒアリングの際に、教育についての価値観や、自分自身が親に過去にどうしてもらったのか、それを再現させてあげたいかを伺っています。
含めて、自動計算では導けないリアルでかかる教育費を想定してシミュレーションを作ることをしています。

お金がかかるのは習い事、そして塾です
『習い事+塾』を考えはじめる年齢は、小4だと思います。
そう、ここまでのはあくまでもスポーツや音楽などの習い事です。塾は入っていないのです。
塾についても費用はピンキリです。例えば有名塾のガチ進学コース。この辺りに入れば、小学生でも月あたり5万円以上は軽くいきます。学年が進んだり、長期休暇の講習も加わるともっとかかってきます。
習い事と合算すれば月7~8万円。子ども2人なら10万円以上もあり得ます。
結果が伴うという前提であれば、親としてはチャレンジさせたいところ。ですが、すべて塾に頼ってしまっては金銭的に多くの家庭でノックアウトします。
とはいえある程度お子さんが大きくなった相談者さんの傾向をみると、子どもを塾へ通わせている保護者は多いです。
教育熱心な立地ほど習い事・塾費用はかかる
土地選びの際に、教育熱心な学区を希望される方は少なくありません。こういうデータは公表されずらいですが、学区と学力は明確に強い関係性があります。
土地価格が高いエリアほど学力は高い傾向があります。これは、シンプルに親の経済力に比例していると読み取るのが自然でしょう。
それもそのはず、そもそも立地がいいところは歩いて行ける塾の選択肢も多いです。同級生に合わせると「皆行ってるから」で自然と塾通いになるからです。
特に中央区中心部の保護者の方の教育投資は多く、私自身も相談者さんから常にいろいろな教育観を学ばせてもらっています。
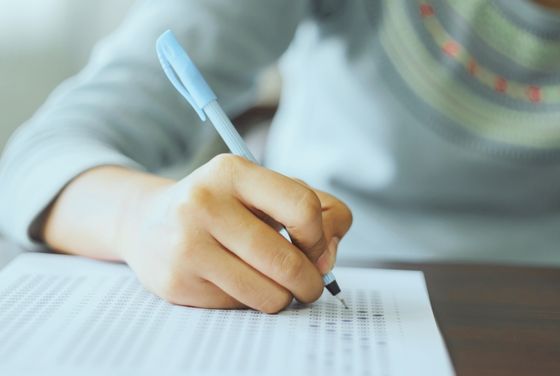
私自身は当初「塾はいいかな」と思っていました。
ですが、そんな私も長男が小4になって考え方を改めつつあります。
よくよく考えると高校受験まであと6年。
6年前、長男は保育園の年小さんでした。正直、親の体感的にあっという間です。
この6年の努力の末の、高校受験の結果いかんにより人生は大きく変わってくる。
もちろん受験に失敗したから終了ではありません。そこからいくらでも挽回もできますし、学歴に関わらずなにか専門性を極めることも出来ます。ですが、ある程度の環境にいたほうが選べる選択肢や、目標に至る道のりへのサポートが多く得られるのは間違いないです。
こう思うのは私自身が進学高校に入りたかったのに、入れなかったという苦い経験からです。
苦い失敗経験が大人になってエネルギーになり、挫折が強力な原動力と化して今があるのも間違いありません。結果的には進学校が良かったということもないのですが、しなくてもいい遠回りを回避させてあげたいと思うのが親心です。
子どもの価値観を最大限尊重するにしても、選択肢は親として提供したいと考えるようになりました。
それができる期間もあとわずか、もう成人まで折り返し地点だからです。
小4の壁の存在
私自身の価値観としては、小学生の頃は自由に好きなように過ごせばいいと思っていました。
どちらかというと体験重視で育ててきて、特に体を動かす系のアシストをしていました。
習い事以外にも私の趣味の登山に積極的に連れていきました。
自然に触れる最適な機会だし、野に咲く草木花々の名前を調べたり、自分の体の動かし方やリミッターをしる機会にもなります。富山県の立山にトライした時は、途中で体力の限界をむかえリタイヤしましたがこういうこともいい経験になります。別にそんなに遠出しなくても五頭山・角田山・弥彦山だけでもう30回以上くらいいっていると思います。
そんな感じでやっていたらなのか、元々なのかは分かりませんが、体力面では兄弟ともにかなりタフになりました。
でも山は私が楽しくてやっているだけで、子どもに特に合わせていません。子どもも私を見ながら楽しみどころを学びます。だからよかったのだと思います。
妻は妻で、積極的にプロの公演や美術館や科学館のイベントにつれていっています。運動も「自分はできないから」と、子どもたちが興味を持った様々な体験会やイベントへと連れ出してくれていました。
こんな感じでこれまでは特に干渉せずに、学習や運動の具合やクラスメートとの付き合い方を俯瞰して見ていました。
10年も一緒にいれば長男の個性や長所と短所もある程度、鮮明に見えてくるようになりました。
鮮明に見えるようになってきた今こそ、親として手を差し伸べる最初の機会が訪れます。
それは小4の壁です。
私は大学で教育学を学んでいて、小学校教諭の資格をとりました。
しかし教員として実務経験はありません。
その講義の中で学んだことを、おぼろけながら覚えていて、学び直しをしています。
小4の壁とは?

小4の壁とは、以下の通りです。
●子どもの変化
授業が一気にレベルアップし抽象的・論理的になり、勉強についていくのが難しくなる子が増えてきます。たとえば算数で割り算・分数、理科や社会でもより複雑な内容が出てきます。
●自主性や自己主張の芽生え
親の指示通りに動かず、自分の考えを主張するようになる一方で、感情のコントロールが難しくなる場面が増えます。
プレ半反抗期やギャングエイジと呼ばれる心の成長過程です。
●人間関係の複雑化
友達との関係が深くなり、グループ行動や「仲間外れ」などの問題が生じやすくなります。
特に算数で割り算を頭で理解できないとその後の算数・数学、学習全般で大きく苦労する傾向が強いようです。
息子から「割り算が苦手」という言葉を聞いた時に、小4の壁のことを思い出しました。これを放置してはならないと思いました。
親が介入できる最初の大きな機会
長男の学校のテストの点が低いとは思いません。
それなのに「勉強が苦手」というのが気になりました。まずは根本的に「なぜ勉強をする必要があるのか?」ということをしっかりと話していきたいと思いました。根底となるマインドセットがまずい状態なのです。
一緒にお風呂に入っている時にいろいろと説いているのですが、最初ウザそうに聞いていたものの、しっかり説明をすると内容を理解してくれるようになってきました。
自主性については、大前提として子どもも1人の人間です。
人間なんて基本、誰かの指図を受けて動くものではありません。感情の動きがあって当然です。そこは人生の先輩としてどっしり構えますし、そもそも自分も人格者でもありません。
人間関係については、親としては干渉せずに(というかできないし)逃げ場を提供、学校とは違う自分の能力を発揮できる場を習い事や課題活動で今まで通り提供すれば良いかなと思っています。
今のところ人間関係は特に問題ないみたいですが、そんな雰囲気を感じることがあれば「いろいろ嫌になったら、一緒に山登って帰りに温泉いってラーメン食べよう!」と誘おうと思います。
そこで「どうせ相手は変わらないから、自分が変わるしかないんだよ」とウザがられながらも教えてあげようと考えています。
結論、塾を始めることを提案してみた
そこで結論なのですが、子どもに塾を提案しました。
はじめは「勉強が苦手だから嫌だ!」と言っていました。
「だよね。まあ、そうくるだろうな」と100%思っていたので、「なぜ塾に行くのか?勉強をなぜいまがんばるのか?」を、運動の習い事の帰り道の車の中で2人の時に説明しました。
翌日に本人なりにいろいろ考えたのか「やりたい!」となりました。
本人の中の目的と勉強の必要性が何かしらリンクしたのだと思います。
当然ながらゲームで釣るようなことはしていません。
とりあえず自主性の獲得には成功しました(笑)
何事も自主性は超大事です。
※例えば、もしあなたがライフプランを作ろうと思った時に、きっかけが住宅会社に言われたから作ろうと思うのと、自分で調べて必要だから作ろうと思い行動したのとではその後の結果の生かし方に雲泥の差がでます。
塾の目的を親として何に設定するのか?
塾については、私は極めて郊外に住んでいるので“公文式”以外選択肢がありません。
さすがにもう習い事の送迎回数を増やしたくないし、歩いて行けるところが希望です。
※このあともう少し調べて、週1通学、あとはオンライン遠隔というシステムがあることも知りました。選択肢はないと思っていただけで、実際に調べたり講師の先生にいろいろ聞いたりすると方法はいくらでもあるようです。
私自身も公文OBで大学生の時にアルバイトで公文の先生をしていました。そのため、教材の意図と目的がわかるのはメリットです。公文のよさは学力向上よりも、習慣化です。そして自信がつきやすい教材になっています。(ただ合わない子は、全く合わないので注意)
間違った問題を繰り返し解いて、分かるようになるまで解く。答えは教えてもらえない。試行錯誤して自力で解く。
そこでまずは小4の壁となる割り算、分数・小数を繰り返し、苦手を克服して欲しい。
大丈夫、すぐにできるようになるので、そこで自信がつきます。
学習面にといての壁は、私の見立てでは一瞬で粉砕できるはずです。
公文の先生は教えることではなく、丸付けと見守りが仕事なので、あとは自主性を促してどんどん階級を飛ばして学んでもらいます。
小5できっと中学レベルに到達できると思います。
そうなると自信が生まれます。私は小学生の時に運動が苦手だったので、勉強をかんばっていることが自分の中の貴重な心の支えでした。
すでに運動が得意な長男は、勉強もとくい、と思えたらもっと自信を持つことができるでしょう。
勉強でもなんでもできるようになれば楽しくなります。
そこまでは親がきっかけを作れます。

勉強に適性があるかを見極める
その後は、自分の子どもであれ、人を変えることはできません。
勉強も適性がないかもしれないし、周りの子よりも集中力が少ないかもしれません。でもそれが早期に分かれば別な進み方も見えてくるし、レールから敢えて脱して突き抜ける人生にチャレンジする可能性も見出せます。
一方で適性があれば、早めに選択肢を与えてあげる事は、子どもにとって一生の財産になります。何事にも代えられない価値です。
ここでそのカードを親が切れるかは、その時の家計にわずかでも余裕があるかどうかに尽きます。
将来的にしたいことができて、そのハードルが学力によるふるいによるものであれば、あとで努力を始めても先に努力をしている子たちに追いつくことは容易ではありません。無理と言ってはいけませんが、現実的には相当厳しいと思います。
公文の先生を当時やっていて分かったことは、伸びる子は一発で見てすぐわかる。伸びない子は先生がいくらがんばっても難しいということです。
正直、塾に通った「だけ」成績が大きく変わる子というのは稀で、内なる動機づけを含めての資質や、親からの影響が大きいところがあります。
結局、自主性というか、勉強を面白いと思うかどうかに尽きます。その最初のスイッチを起動させてあげられるかどうかは親にあると思います。塾はツールでしかありません。身近な大人である親が自主性を伸ばす努力をしないとどうにもならんという記憶があります。
塾にお金を出してあげる事で、親として責任が終わるわけではないのです。
そういう保護者はうまくいかないということを、先生サイドの時に思っていました。今は、自分がそういう親にならないように気を付けたいと思います。
教育費は思ったよりもかなりかかります
少し話がそれてしまいましが、教育費は思った以上にかかる可能性が高いということです。
けれど中長期的なライフプランを作っていて思うことは、お金の使い時どきが人生でどこにあるのかを知ることができるのです。
お金を大事に握りしめて、老後に残しても使えません。
老後に贅沢するためにお金を貯めているのではありません。
「ここぞ!」という場面が来た時に家計資本を投下していくのです。
私の場合は、今がちょうど最初のその時かなと思います。
人生を振り返ってみたときに、「あの時、なぜわかっていたのに子どもに自分の時間を割かなかったのだろうか。」とかお金をケチってしまったのだろうかと後悔したくありません。
新潟住まいのお金相談室の相談者の方は、子どもがまだ0歳前後の方が多いです。その段階では教育費の話がきっとまだピンと来ないはずです。私もそうでした。
でもあなたも10年後、そう思うときがきます。それは勉強かもしれませんし、それ以外の教育や習い事かもしれません。
「子どもを応援したい」と思ったときにだせるお金や時間があるのって、親としての喜びのひとつだと思うんです。
将来を見据えて少しでも参考にしていただければ幸いです。

PS
簡単に自動計算されるシミュレーションではなくて、あなたのフィットしたあなたの価値観を反映したライフプランを作ることが大事です。
住宅購入費は教育費に強く影響を受けます。
教育費を加味した無理のない住宅ローンの額を知りたいならマイホーム予算診断サービスをお申込みください。
ライフプランはFPなら誰でも作れるわけではありません。
私は土地を買って住宅を購入し、今はリフォームも実施し、子育てをし、今は教育費がガチでかかりはじめてヒーヒー言っている段階です。
こういったリアルを積めば積むほど、相談者に寄り添ったいい提案ができると思います。
あなたと一緒にこれからもがんばっていきます。
保険や住宅を売ることを目的にしない住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして、100%顧客サイドで顧客の理想とする家を安心・納得して買えるようにアドバイスを行う。そのスタイルが支持され、新潟県全域から年間100件以上の相談依頼を受けている。