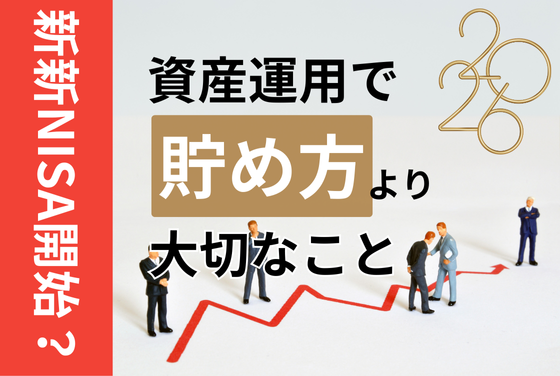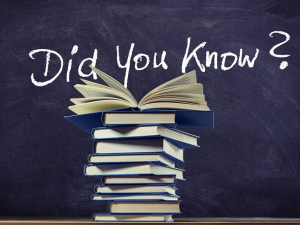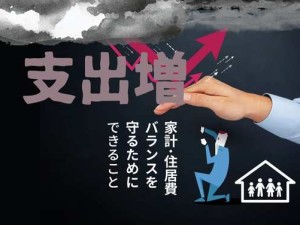2024年からルールが変わって注目を浴びた新NISA。今後もっとよくなる方向で動いているみたいですね。
ジュニアNISA廃止後空白になっていた未成年非課税口座の復活が目玉になりそうです。
ただ復活ではなく、対象の年齢層や選べる商品が増え、より多くの人にとって使いやすい制度になっていくようです。
ただし、選択肢が広がるからといって「なんとなく投資しておけば安心」というわけではありません。
実はNISAを活用するうえで一番大切なのは、制度の内容ではありません。
それよりも「そのお金を何のために使うのか」という視点が大事なんです。
今日は私自身の経験も交えながら、「資産をどう使うか」という視点の重要性についてお伝えします。
NISA拡充で広がる選択肢、大切なのは「目的」
2024年から始まった新NISAは、すでに多くの方が利用し始めています。
そして今後の拡充により、さらに使い勝手がよくなっていくことでしょう。
具体的には、これまで投資対象として認められていなかったシニアに人気の毎月配当金を吐き出すタイプの投資信託や債券投資信託も購入可能になること。さらにつみたて枠に限り未成年者も口座を持てるようになることなどが予定されています。
さらにさらに、保有している商品を別の商品に入れ替えられる「スイッチング」が可能になるなど、iDeCoでしかできなかったことがNISAでもできるようになり柔軟性も高まります。
こうした制度改正は、利用者にとって選択肢が広がる意味で大変有益です。
しかし、それ以上に大事なことがあります。
それは「何のために投資をするのか」をはっきりさせることです。
投資はあくまで「手段」。
目的そのものではありません。
老後資金の準備
教育費の積み立て
将来のマイホーム資金
あるいは旅行や趣味のための資金づくり
投資の目的は人それぞれです。
NISAの拡充で可能性が広がる分、「とにかく投資できるなら何でもいい。」と始めてしまうと、自分の生活や価値観とずれた投資になってしまう恐れもあります。
だからこそまず「なぜ投資するのか」「そのお金をどう使いたいのか」をしっかりと考えることが必要なのです。
それをしておかないと、今の貯蓄を今の喜びに変えず、未知数な未来に投げてしまうだけになってしまいます。

FPが旧つみたてNISAを部分解約した理由
少し個人的な体験をお話しします。
私はこれまで旧つみたてNISAを利用して、複数の投資信託を購入していました。その中には「8資産均等型ファンド」という、国内外の株式・債券・不動産など幅広い資産に均等分散して投資するファンドも含まれていました。
一見するとバランスの取れた商品です。
ですが、実際に運用してみるとお金が増えたことには増えたました。ですが、利益のほとんどは1ドルが100円位に買ったものが150円になったという「為替差益」。
つまり、資産そのものの成長というよりも、円安によって見かけ上の利益が増えている状況だったのです。特に2024年から2025年にかけて、ドル円は150円近辺まで円安が進みました。
このまま円安が続く保証はありません。
むしろ為替が反転すれば利益は一気に削られる可能性もあります。

そう考えた私は、「ここで利益確定して現実の生活に活かした方がいい」と判断しました。
結果として、旧つみたてNISAの一部を解約し、利益を確定させることにしたのです。
投資信託は長期で持つのが基本と言われます。
が、目的に応じて「使うタイミングを選ぶ」こともまた投資の本質なのです。投資に慣れてくると、買う時よりも売る時のほうが難しいことに気づきます。最終目的はあくまでも売って利益を得ることです。
自分の生活がより良くなるように、不労所得の恩恵を受けるのが投資の醍醐味と言えます。
では、解約して得た資金をどうしたのか。
我が家はその一部を使って日常使いの新車を購入しました。
「え?車くらい、貯蓄で買えるものでいいじゃない」
「せっかく増えたお金をまた消費してしまったのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、私はむしろ合理的なお金の使い方をしたと考えています。
投資で得た利益を「車の購入」に充てた理由
まず、最近の車はマイナーチェンジという名の値上げを繰り返しています。物価や人件費の急上昇に、発売当時の定価が合わなくなっているからです。
さらに、事故防止のための先進設備の進化や排ガス規制の影響もあります。結果として数年前に比べても、大衆車の新車価格は大幅に上昇しています。(省エネ性能や脱炭素が必然となっている住宅も一緒です)
さらに今後10年、物価や人件費の上昇、環境規制への対応コストなどから、車の価格は下がるよりもむしろ上がる可能性が濃厚でしょう。つまり、今のタイミングで購入して長く乗ることは、将来のコスト上昇を避ける有効な手段になり得るのです。
私は投資で得た利益の一部を確定させて車の購入に充てることで、「これから10年間の車にかかる物価上昇リスクを先取りして排除した」と考えています。
結果として、投資で得た利益を単なる贅沢に使うのではなく、将来の生活コストを安定化させる投資的な消費に変えたのです。
これから10年間の運用益よりも、10年間の自動車支出を固定させることを取った形になります。

将来の支出を減らすことも、将来の資産を増やすことにつながる
もちろんこれがベストかどうかは正解は分かりません。
ですが、売却した投資信託は為替差益がメインでした。
そのため
・今後円高傾向になる可能性を含み、為替だけで今後10年間大きな利益を出すのは厳しい
・さらに日本株・世界株は直近で高値圏にあり一度利確するのはいいタイミングかも
という2つの仮説を立てました。
自分で納得の上行動すること、投資は時価でしかなく、利益確定する行為にも慣れておくことに意味があると思っています。
大切なのは、将来に向けてお金を増やす方法は「運用で資産を大きくする」だけではない、という視点です。
ライフプランにおいては、これからかかる支出を減らす工夫や、将来の負担を軽くする手立てを先に打っておくことも立派な資産形成の一部になります。
今回の車の購入も、まさにそうした考え方の延長線上にあると言えます。
「物価高騰が続く住宅を早めに買っておいた方が良い。」と考えることも、これに似た考え方であると感じます。
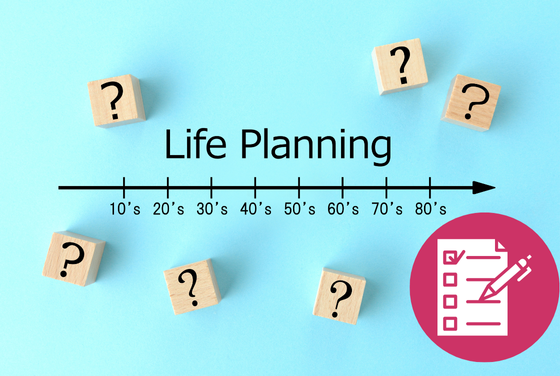
「貯める」よりも「どう使うか」を意識しよう
NISAの拡充は、多くの人にとって資産形成の可能性を広げてくれる素晴らしい制度です。しかし、制度の枠や選べる商品の種類以上に大切なのは、「そのお金を最終的にどう活かすのか。」という視点です。
貯蓄や投資はゴールではありません。
老後に安心して暮らしたい。
子どもに教育の機会を与えたい
生活をより快適にしたい...。
こうした目的のために投資をするのであり、その目的がぶれない限り投資の判断軸も定まります。
今回の私のケースでいえば、「為替差益を活かして車を買い、将来の物価上昇リスクを避ける。」という使い方が最も合理的でした。
ここで注意したいのは、資産運用の残高を増やすこと自体が目的になってしまうと、マイホーム購入費用を必要以上に抑え込んでしまう傾向がある点です。
せっかく家を建てるのなら、金額だけで判断するのではなく、無理のない範囲で自分たちが快適に住める場所や住まいを選ぶことが重要です。
適正コストはライフプラン全体を考えないと見えてこない

これから何十年も住む家なのに、予算の関係で快適でない家を住む。デメリットを多くの人は過小評価していると私は思います。
しかし家を買う前には、この「快適に暮らすための適正コスト」という発想になかなか気づきにくいのも現実です。
だからこそ資産運用だけでなく、ライフプラン全体のバランスを考えることが欠かせません。
人生全体で考えたときに、自分のお金をどのタイミングでどう使うことが満足度が高いのか。
このことを考えてみることをおすすめします。
特に30~40代では、住宅や教育投資、家族での思い出作りなど、自分自身や子どもの将来などにおいて生きたお金の使い方ができる可能性が高い時期です。過剰に老後にお金を回しすぎない、という意識を持つことは間違いなく幸福感に直結します。
これからNISAを始める方も、すでに利用している方も、ぜひ「貯めること」だけではなく「どう使うか」にも意識を向けてみてください。投資で得た利益を、未来の生活を豊かにする形で活かせるかどうか。
その判断こそが、画面上の数字で一喜一憂するだけではない、本質的な資産形成の成否を分ける大きなポイントになります。
PS 資産形成をふまえてマイホームを検討したい あなたへ
なお、マイホームを検討している方は「いくらの家なら無理なく安心して買えるのか。」を知っておくことが、資産形成全体を考える上で非常に重要です。
新潟住まいのお金相談室では「マイホーム予算診断サービス」を行っています。
住宅ローンの返済だけでなく、教育費や老後資金とのバランスを踏まえた上で適正な購入予算を診断します。
これから家を建てたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
保険や住宅を売ることを目的にしない住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして、100%顧客サイドで顧客の理想とする家を安心・納得して買えるようにアドバイスを行う。そのスタイルが支持され、新潟県全域から年間100件以上の相談依頼を受けている。