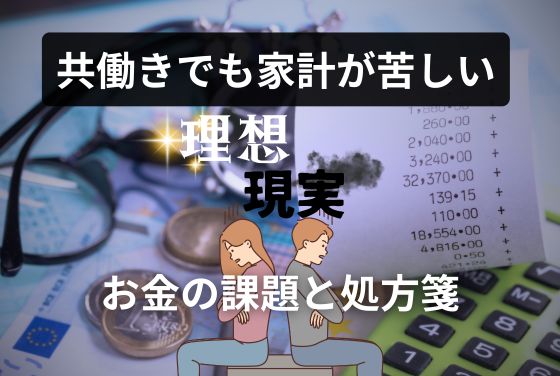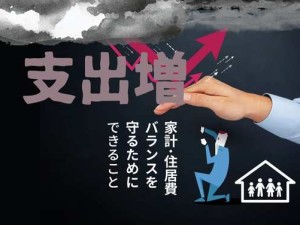あなたは理想の世帯年収と聞いて、いくらくらいを思い浮かべますか?
マイナビが2024年11月に実施した「共働き正社員の仕事や私生活に関する意識調査」によると、理想とする世帯年収はなんと平均1126万円。
一方で、実際の平均世帯年収は約806万円。
なんと、320万円ものギャップがあることが明らかになりました(!)。
また、「家計が苦しい」と感じている人は46%。
共働きであっても経済的な不安を感じている現実があるそうです。
ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から見ても、これは現実を的確にとらえている興味深い調査結果だと感じました。
「生活が苦しい…。じゃあ、いくらあったら生活が楽になるの?」という具体的な数値が可視化されているからです。
実際、年間で320万円にもなると、賃上げや減税だけでは到底追いつきません。他力本願ではどうにもならないのです。
つまり、個々の家庭の地道な努力が差を生む時代に本格的に入っているのだと、改めて読み取れます。
今日はこの調査結果をもとに、共働き世帯を取り巻く「理想と現実のギャップ」。そしてその具体的な解決策について考えてみたいと思います。
特にこれから家を建てることを検討している方にとって、
「家計の余裕がどの程度あるか」
これは住宅ローンの組み方や生活設計を考えるうえで非常に重要な視点になります。
【理想とする世帯年収は1,126万円】のリアル
「理想の世帯年収1,126万円」という数字を見て、あなたはどう感じたでしょうか?
高すぎると感じる人もいれば、妥当だと感じる人もいるかもしれません。
ちなみに子どもがいる世帯では理想年収は1,247万円ということです。
私はこの数字は的確で、むしろ現実的だと思いました。
これから新築住宅を計画しているご家庭や、小さなお子さんのいる世帯では、教育資金・住宅ローン・老後資金という3大支出をすべてまかなう必要があります。
そうなると、年収1000万円以上を目指すのはごく自然な感覚です。

たとえば新築住宅では、土地代・建築費・諸費用を合わせて5000万円超の支出になるケースも多く、35年ローンで月13〜15万円の支払いになることが一般的です。これに教育費や生活費が重なれば、想定以上に出費がかさむのは当然です。
つまり「理想の年収」とは
住宅ローンをムリなく支払い
子どもに満足に教育費をかけ
長期休暇では家族旅行にも行けて
老後資金も着実に貯められる...
今の日本において不自由のない生活を実現するための現実的な目標値なのです。
家計が苦しいと感じる根本的な理由
調査では、家計が苦しいと感じている人の世帯年収は平均716万円。
逆に「苦しくない」と感じている人は平均886万円。
2者間には、約170万円の差がありました。
FPとして現場で接している感覚からしても、これは非常にリアルな数値です。
新潟で5000万円クラスの家を購入する場合、世帯年収900万円以上がひとつの目安になります。
これはあくまで「苦しくはない目安」です。余裕があるとはまた別物です。
「家族旅行にも行きたい。」「好きな車に乗りたい。」となると、さらに+200万円程度は欲しくなります。
つまり800〜900万円でも家計は回せるものの、あと+100〜200万円が“ゆとり度”を大きく左右するのです。
そう考えると、理想とされる世帯年収の数字も納得がいきます。
ちなみに新潟のような地方都市では、首都圏よりも物価や住居費がやや低いです。そのため、子育て世帯でも年収1000万円を超えると余裕を感じやすくなる傾向があります。
管理されていない「なんとなくの支出」
共働きだと日々の忙しさから、家計簿をつける時間がなく、クレジットカード払いやサブスク契約など、「気づいたら引き落とされている支出」が積み重なりがちです。外食もついつい多くなってしまいますよね。(しかも外食は最近とても高い)
夫婦間でお金の共有ができていないケースでは、お互いの支出を把握できず、「どこから見直せばよいのか分からない。」という相談もよく受けます。
たとえば、夫婦それぞれがAmazonプライムやSpotifyに個別で加入し、一世帯で課金しているケースも散見されます。笑い話ではなく実際によくある話です。

固定費の見直しが進んでいない
「固定費」は、一度設定するとそのまま放置されやすい項目です。
例えば、賢いようでまだもう一声だったりするものとしては
- auからUQに切り替えて終わり ⇒ もっと安くできる
- 保険屋さんの相談窓口で保険の見直し ⇒ 今より少し良くなっただけで、そもそも不要な保険も
- 車にこだわりがないから安い中古車 ⇒ 修繕・維持費やリセールを考えると年あたりのコストがかえって割高
- 燃費重視でハイブリッド ⇒ トータルコストはガソリン車がトク
一件見直しや効果的な方法をしているようでも、まだまだ見直せる余地は多くの家庭で見られます。
特にこれから住宅ローンを組む方は、これから発生する最大の固定コストである住宅費をどう設定するかが家計のカギです。
月々の返済額だけでなく、将来的な金利変動リスクにも備えておく必要があります。
住宅ローンは借入額が大きいほど金利変動の影響も大きくなるため、慎重な設計が求められます。ここを間違えると、細かい支出の見直しではどうにもならなくなってしまうからです。
解決のカギは「家計の見える化」と夫婦のチームワーク
この話は今に始まったことではなく、昔から「平均年収+α」がゆとりを生む基本原則でした。
つまり、早くから気づき、改善に向けて動いた人の勝ちです。他の人と同じような行動をとればとるほど平均に収縮してしまうからです。
では、共働き家庭が今からできる具体的な対策とはどのようなものがあるでしょうか。

① 家計の全体像を整理する
まずは夫婦の収入・支出を合わせて、全体の流れを可視化すること。
特に家を建てる前には、「住宅ローンを組んだ後の家計変化」を感覚的にも理解しておく必要があります。
購入後に「返済はできているけど貯金が全く増えない」という状態になってしまった場合、それは危険信号です。
ライフプランの事前設計で、ほとんどの失敗は防げます。
② 目的別の貯金と支出の明確化
将来に備えるには、「何のために・いつ・いくら必要か」を明確にすることが大切です。
特に教育資金と老後資金は時期が先ですから資産運用と相性が良いです。
資産運用によって、労働収入以外からも準備する方法を取り入れることで、不安を「戦略」に変えられます。
③ 夫婦で定期的に“お金会議”を
年に1〜2回で構いませんので、家計の方針を話し合う夫婦会議を開きましょう。
住宅購入前は、人生でもっとも大きな金額が動くタイミングです。
この二度とない“若くて大きなお金を動かす”前のタイミングを、見直しの最大チャンスにしましょう。
そして貯めるだけではなくて、節目の目的を達成ごとに夫婦のご褒美を設けましょう。
※私は昔目標を達成した時に、東京駅の東京ステーションホテルに泊まりました。いい思い出です。
家を建てるなら、お金の見直しも「今がチャンス」
「家を建てること」は人生の大きな選択になります。
そして「お金と向き合うこと」も同じくらい大事な選択です。
FPとして私は「家づくりをきっかけに家計を見直し、将来設計を整える」ことを何よりおすすめしています。
理想の年収を力技で稼ぐことも一つの道で若い人には正直おすすめです。今の仕事に見切りをつけて、理想とするステージに自分自身が這い上がる努力は若いければ若いほど身になりやすいです。若くして蓄財すれば、さらに運用によってパワーが増すからです。
でも実際問題それが難しいことも知っています。その場合は、夫婦で計画と戦略を持つことが何よりの武器になります。
私の提供する《マイホーム予算診断サービス》では、家を買う前にライフプランを一緒に考えるサポートをしています。
「建てた後に後悔したくない」という方は、ぜひご活用ください。
この住宅購入ルールを知る前に、家を買わないでください
・私が自宅購入で1,000万円損しかけた実例
・住宅ローンを金利の低さで選んではいけない理由
・なぜ住宅会社や銀行が勧める住宅ローンを組んではいけないのか?
・(保険屋さんが絶対に教えたくない)生命保険のお得な入り方
・住宅展示場や完成見学会に行く前に、絶対にやること
・住宅購入で将来赤字になる家計を黒字転換させた改善点の具体例
・住宅購入後も住宅ローン返済の不安なくお金が貯まる家計を作る方法
などなど、
今まで対面セミナーのみでお伝えしてきた、新潟で家を建てる多くの人が知らない
「初めての住宅購入で失敗しないためのお金のルール」をオンラインで初公開!
オンラインセミナー受講は完全無料です。下記のボタンをクリックしてお申込みください。
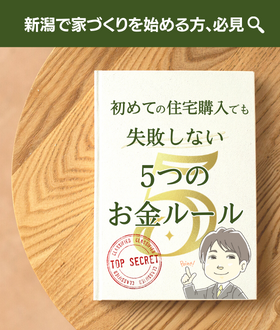
保険や住宅を売ることを目的にしない住宅購入専門のファイナンシャルプランナーとして、100%顧客サイドで顧客の理想とする家を安心・納得して買えるようにアドバイスを行う。そのスタイルが支持され、新潟県全域から年間100件以上の相談依頼を受けている。